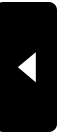2011年11月06日
バックアップに良いのはどの方法か?(ローカル機器比較)

青紅葉
S30 / RawTherapee
S30 / RawTherapee
今、写真データのバックアップについて考えている。
東日本大震災では「アルバムをまず探し出した」という報道が印象的だった。
古いアルバムをめくりながら「誰々は、子供のころの誰々によく似ている」という、
たわいのない親類同士の話も、写真があってはじめて楽しめる、ということにも最近気づいた。
実家は木造なので、地震だけでなく火災のリスクもあるし、
古い写真はデータ化してバックアップすれば万全だろう。
でも、まずは息子の写真からだ。
PCが壊れ、この3年間の写真を全て失った、という人が身近にいた。
明日はわが身かもしれない。
K100Dのメモリーカードにはまだ余裕はあるので、デッドラインは今年中くらいか。
ざっと半日検討した結論から言えば、
外付けHDDとクラウドを併用した三重バックアップ、が現実的な気がする。
今日はまず、ローカルIT機器の具体的な比較を行った。
-----
前提:
カメラのメモリーカード内のデータは、いったんPC内臓HDDにコピーする。
(鑑賞や現像処理等のメインマシンはPCであるため。)
比較するバックアップ先候補:
・SDカード(カメラのメモリーカードを消去しない)
・外付けHDD USB2.0(PCの内臓HDDをミラーリングする)
・DVD-Rメディア(PC内臓HDDのデータを書き出し、別の場所に保管する)
今回、追加投資の必要なBlue-rayやUSB3.0等の新規格品は見送った。
比較結果:

考察:
分かりやすいコスト比較として、データ単価を価格/データ量で算出した。
(メモリーカードは安くはなったが、まだまだHDDには及ばないようだ。)
バックアップ作業の手間を手順数と時間で考えてみた。
手順は、電源オン・オフやメディアの出し入れなど。時間は、データ転送時間だ。
以上、左から三項目だけを比較すると、
1)データ単価が高くて手間がないメモリカード。
2)データ単価は低いが手間も少ないHDD。
3)データ単価は低いが手間も多いDVD-R。
という分かりやすいトレードオフ関係が見られた。
一見、HDDが手間の割りにコストが低いので一番よさそうなのだが、
小売価格や故障時に損失するデータ量(容量)となるとDVD-Rと逆転する。
寿命3年ともいわれる外付けHDDを過信するのは禁物だ:)
内臓より先に外付けが壊れたら、「更新コスト」はかなり高くつくことになる。
(上の表では更新コストは比較していないが、だいたい小売価格/数年だろう。)
最後に保管場所だが、住宅事情からは無視できないファクターだ。
DVD-Rが一番かさばる。
メモリカードは、整理用のファイルを買えば何とかなりそうだ。
以上から、ファイル容量が少ないのなら(1)SDメモリカード、
Rawデータを残したいのなら(2)外付けHDD、
というのが我が家の現実だ。
ただ、タイの水害で、HDDはここのところ値上がりしているようだ。
国内メーカーも代替調達に走っているようなので、ここは冷静に様子を見たほうがいいだろう。
なお今回は、価格コム定番Shopの値段を使用したので、
対面販売の店舗ではもう少し高めかも知れない。
他のデータもだいたいの平均的なところを使っている。
メディアの価格は、一年後には1/2~2/3程度に落ちていることだろう。
2011年11月04日
発熱中の指はさみ事故

楠
S30 / RawTherapee
先月アップロードしていた最後の楠の写真。
週末は全国的に天気が悪いので、風邪が治っても家に缶詰かな。
------
昨日より体調が悪く、微熱もあるようだ。
仕事を休んで一日寝ていたが、まだ発熱している。
昨日、データのバックアップについて思い出したので、
各種手段を調べているが、熱のある頭ではうまくまとまらない。
今のところ、
・クラウド(写真共有サービスなど)
・ローカルHDD
・SDメモリーカード
の三者を候補に挙げている。
熱が下がったら、特徴をまとめるつもり。
------
育児日誌:
ぼーっとしているので、風呂場の戸で息子の指を挟んでしまった。
息子は、こちらが風呂に入っているのに気づいて、扉をあけようとしていた。
こらー、と言いながら扉を押したのだが、いつものようにしまらない。
変だな、と思いながらさらに強く押してしめると、
反対側で泣き声がして、指をはさんだのに気づいた、という顛末だ。
ほとんど隙間のないところに人差し指と中指の先がはさまれたようで、
分かったときには青くなったが、幸い骨折はしていなかったようだ。
息子は、やりたいことに対しての執着が強い。
姿が見えないときほど、特に気をつけなければ。
2011年11月03日
バックアップはどこでしようか?

桜
S30 / RawTherapee
もみじより一足早く桜の葉が色づき始めた。
朝日を通して虹色にも見える。
焦点距離が短くてボケ難いコンパクトカメラでは、
木の葉を影絵のように撮ると、背景が黒く沈んでいい感じ。
S30 / RawTherapee
もみじより一足早く桜の葉が色づき始めた。
朝日を通して虹色にも見える。
焦点距離が短くてボケ難いコンパクトカメラでは、
木の葉を影絵のように撮ると、背景が黒く沈んでいい感じ。
-----
またまた風邪をひいてしまった。
家族全員が次々にかかっていくので、流行性だろう。
検診の人ごみで持ち帰ってきたのをうつされたようだ。
これもグローバル社会の「恩恵」か。
何か良いことがあれば悪いこともある。
変化とはそういうものだろう。
グローバルと言えば、タイの洪水が気になる。
日系企業工場の被災ニュースを見ると、
現地駐在員の方々の苦労がしのばれる。
卑近なところでは、ハードディスクが値上がりしていると聞いて、しまったと思った。
写真データのバックアップ用をまだ買っていなかったのに。
G12で撮る写真は、1000万画素のせいか、データ量が大きい。
Raw撮影の楽しみを知ってしまったので、SDカードはすぐにいっぱいになる。
当面は、気に入った写真のJPEGのみをクラウドスペースに上げようかと考えている。
ただ、クラウドをバックアップ用に、という話は他でも良く聞くが、
データセンターがどこなのか分からないので、素人にはリスクの算定が難しい。
そのうちHDDを買わなければ。
------
testimonial 証拠(の)
nonetheless それにもかかわらず
astound 驚かす
astounding おどろくべき
resurrect 復活させる、蒸し返す
2011年11月02日
効果的なヒアリングの学習方法

秋の鱗
S30 / RawTherapee
メタル調の色合いが気に入った一枚。
S30 / RawTherapee
メタル調の色合いが気に入った一枚。
-----
英語学習の必要性を感じ、これまで約1年半、
50分のlectureをmp3で繰り返し聞いている。
半年くらいから、街頭アナウンスの英語が、自然に耳に入るようになってきた。
意味も大体は分かる。
突然街で外国人に声をかけられても、何を言っているかは分かる。
(が、気の利いた返答はできない。。。)
ヒアリングの効果的な学習方法として、同じテープを繰り返し聴く、
という方法を本で読み、愚直に実践してみた結果が功を奏しているようだ。
ただ、シンポジウムの講演などは、語彙不足のため、意味が分からないときがほとんどだ。
そろそろこの学習方法を卒業し、次のステップを考えなければ。
なによりまずは、単語を覚えないといけない。
当初は、一日一単語を確実に覚えようと思っていたが、
役に立つと実感するまでには至らない。。
理由は、使わないから、だろう。
なので方針変更、確実さよりも数を増やすことにした。
再会頻度が高くなり、少しは頭に残るかもしれない。
-----
sophistication 教養
apology 弁明
stare 凝視する
blankly ぼんやりと / 完全に (Blankから来ているのだろう)
stare blankly ぽかんと見る
-----
育児日誌:
息子が言葉を覚える過程が、語学学習の参考になりそう。
彼は、自分を呼ぶ声はもう理解できている。
また、話題が自分のことである、ということも理解していると感じる。
語感で喜怒哀楽が理解できている。
と、いうことは、意味よりも先にトーンを学んでいるのか。
2011年11月01日
植田正治写真美術館(その4)
大山の紅葉
K100D
今年は遅いと言われる大山も色づき始めたようだ。
写真は、2009年の大山登山口付近での一枚。
少し歩いただけで、原生林の静寂が身を包んでくれた。
K100D
今年は遅いと言われる大山も色づき始めたようだ。
写真は、2009年の大山登山口付近での一枚。
少し歩いただけで、原生林の静寂が身を包んでくれた。
-----
植田正治氏は、地元の風景や家族の写真を作品の中に多く残された。
演出写真と評されるその作風は、いわゆる一般的な写真とは一線を画す。
念入りに被写体の配置と光が考えられた、その作品への評価は人それぞれだろう。
コラージュ?、前衛美術?、というような作品群も面白いのだが、
一番好きなのは家族の写真だった。
あの時はまだ息子は存在しておらず、公私ともども辛い時期の最中だった。
植田氏の家族に向けられた暖かいまなざしを感じさせる作品群に
とりわけ心惹かれた理由には、そんな状況のせいもあったのかもしれない。
-----
育児日誌:
先週末は、田舎に住んでいる94歳の祖母に息子を会わせて来た。
「もう死ぬ」というのが口癖のようだが、
杖を突いて立ち、歯に衣着せずにずばずばしゃべる祖母は、
かくしゃくとしており、料理は自らこなす。
息子と比べては申し訳ないのだが、妖怪のような存在感であった:)