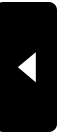2011年10月11日
ファインダーと水準器(G12)
DPP現像メモ:
RGBタブにて
・トーンカーブ調整(S字にして基準線より下方へ)
RAWタブにて
・ヒストグラムの上端を下げて全体を暗く
・ハイライト(1)
・シャドウ(2)
・アンシャープネスマスク 強さ(0)
-----
G12に付いている電子水準器が便利で多用しているが、
縦位置での検出の問題に気がついた。
水平方向が正しく検知されるのは、カメラを右回転したときだけなのだ。
シャッターボタンが下に来る回転方向のみ、水平が正しく検知される。
(ボタンが上方向に来る左回転の場合は、水平が3目盛りほど左にずれている)
Webでこの問題について検索すると、同様の点が二カ所で指摘されていたので、
この辺は技術の限界なのかもしれない(仕様?)。
カメラを構えるときの基本、左手一本でカメラを支える、
という撮影方法では、この問題には気づかないだろうけど。
しかし、右手のみで縦位置で撮る時は、左回転のほうが押しやすい。
両手では構えづらい状況のときほど、水準器を頼りにしたく、
ぜひ両方の回転方向で水平が出るようにして欲しいものだ。
そこで、水準器が使えない場合を想定して、
表示設定で、
●DISP1に電子水準器
●DISP2にグリッドライン
とした。
片手縦位置撮影時は、グリッドラインで水平の目安とする。
-----
育児日誌:
車のオイル交換へ行ったら、ディーラーでWRXの模型をもらった。
昨年、キャンペーンで配布していた記念品らしい。
Wラリーからは撤退したが、WRXは今でもラインナップされているようだ。
テレビの脇に置いておいたら、車好きの息子が必死に取ろうとしていた:)
しばらく様子を見ていたが、届かないようだったのでそのままに。
しかし数時間後、懸命に体を伸ばし、腕を伸ばして、
とうとう掴み取ることに成功してしまった。
残念ながら、これは対象年齢15歳以上。食器棚の脇に移動した。
2011年10月10日
パエリア
脇役の妖精
G12
パン屋の脇の花壇にて。
真昼の撮影のため、JPEGファイルは花弁が白っぽくなっていた。
DPPで現像し、花弁の紫色をはっきりさせた。
G12
パン屋の脇の花壇にて。
真昼の撮影のため、JPEGファイルは花弁が白っぽくなっていた。
DPPで現像し、花弁の紫色をはっきりさせた。
-----
昨日は、おきゃくさんが来訪。
下記レシピを二倍にしてパエリアを作ったが、
27cmのフライパンでは小さすぎて水気が飛ばず、リゾットとなってしまった。
二人分以上は、オーブンに入るパエリア鍋が欲しい。
■材料(二人分)
肉類 200g
冷凍シーフードミックスや、鶏肉など
炒める香味野菜
玉ねぎ 大1/2
ニンニク 2片
ニンジン 大1/4
具の野菜(あるもので可。量は適当)
ピーマン 1個
パプリカ 1/2個
トマト 中1/2
キノコ 適当
米 1合(180mLカップ一杯)
お湯 約500mL~400mL(トマトの水気による)
■調味料
コンソメスープの素 1個
塩 小さじ1/2
(本場のように「おかず」にする時は、塩はこの二倍で)
ローリエ 1枚
お好みで、レモン汁 大さじ1
(ワインと合わせない時や、トマトが無い時など、酸味を付けたい時)
■道具
直径27cm程度のフッ素コートフライパン
■作り方
カップ一杯(180mL)程度のお湯でコンソメを溶かす。(こがさない為にも、これ重要)
↓
ニンニクをスライスし、フライパンにオリーブオイル大さじ2程度をたらして浸す。
↓
具を切る。
玉ねぎはみじん切りにする。
ニンジン・ピーマン・トマトなどは細かく切る。
パプリカは縦長に厚めに切る。
キノコ類は、火が通りやすいよう、細く裂く。
鶏肉を使う場合は、一口大に切る。
↓
フライパンに火をいれ、弱中火でニンニク・玉ねぎ・ニンジンを炒める。
(パプリカは後で入れる。玉ねぎが透き通る程度まで。焦がさぬように。)
↓
鶏肉を入れる場合は、玉ねぎ等を脇に避け、真ん中で表面の色が変る程度に炒める。
トマトを入れる場合は、鶏肉の次に同様に炒める。
↓
弱火にして米を加えて、油がよくまわるまで炒める。
↓
溶いておいたコンソメスープ(180mL程度)と残りの分量のお湯(300mL程度)を加える。
↓
塩・ローリエの葉などのハーブ類・冷凍シーフードミックスを入れ、米を水平にならす。
(魚介類が解けている時は、10分後に投入する方が良い。)
火加減は、「中火」にする。
↓
煮立ってきたら、お好みでレモン汁を入れ、弱火にしてふたをして 10分煮込む。
火加減は「弱火」。弱すぎると時間がかかるので、とろ火は×。
(これ以降はかき混ぜないこと。米の炊き具合にむらが出る)
↓
パプリカ・キノコ・生の魚介等、あまり火を通さない食材を投入し、さらに弱火で10分煮込む。
(パリッと仕上げるため蓋はしなくてよい。)
底までぱりっとしたら、出来上がり。
■コツ
硬いくらいが美味しいので、こげるのを覚悟で水気は飛ばす。
そのため、魚介は出汁とりと割り切るのが良い。
(あまり高級な食材は使わないほうが良いかも)
フライパンごとテーブルに出すと気分が良い。
鍋しきのさらに下に木のお盆を置いて、テーブルを焦がさぬように。
ホタテ貝柱を入れてみた。これはかなり美味い。
有頭エビは、水洗いして、頭に包丁を入れてから投入する。(出汁をとるため)
ドライトマトは、お湯で5分程度もどしてから包丁で細かく切る。
戻し汁はスープとともに使う。
オリーブをトッピングすると美味しい。
-----
育児日誌:
息子と誕生日が二日違いの男の子が遊びにやってきた。
すでに二足直立、ソファにつかまり、つたい歩きをしていた。
彼のほうが動きがすばやく、いつもおもちゃを先に取られてしまっていた。
一方で、手・指の動きは息子のほうが細かいようだ。
パンをつかんで食べる動作を「すごい!」と褒めてもらっていた。
子どもによって発達の仕方は全然違う。
2011年10月08日
万事が「ソフトウエア」で説明できる
営業終了
G12
競技馬の畜舎での一枚。
G12の電子水準器は便利である。
格子の水平が気持ちよく決まる。
G12
競技馬の畜舎での一枚。
G12の電子水準器は便利である。
格子の水平が気持ちよく決まる。
------
Steve Jobs氏の逝去に伴い、今まで寝ていたITネタを起こしている。
少し寝不足気味である。
Apple社の躍進を競合他社が真似できない競争優位性について考えると、
コンテンツ配信事業へと舵を切ったことで説明される。
ハード主導の事業からソフト主導の事業へ。
そういえばIBM社も、PC事業を売却しソフトウエア事業に力を入れて再成長した。
IT業界だけではない。
スーパーの売り場を見れば、加工品だけでなく、野菜から肉にまで、
健康とか美味しさとか、作り手のこだわりだとか、
そのようなソフトウエア・・・というか、物語があふれている。
これを買えば、こうなりますよ、という物語だ。
末端商品を売ると言うことは、ソフトウエアを売るということなのだ。
今起こっている変化は、このソフトウエアは何か?という問いを立てれば説明できそうだ。
タグ :G12
2011年10月07日
訃報:Steve Jobs
K100D DA FISH-EYE 10-17mmF3.5-4.5ED[IF]
スティーブ・ジョブズ氏の訃報は、仕事中に偶然知った。
ここ数年の報道から予期してはいたけれども、そのときを迎えた今となっては寂しさを感じる。
「Macintoshを使う理想の機会」が永遠に失われたような、そんな気分がした。
Apple社のコンピューターを初めて触ったのは、
Macintosh Classic? ダルマみたいなかわいらしいPCだった。
お金持ちの文具という印象で、自分とは縁遠い世界と思っていたら、
仕事でシステムの入れ替えをするほどに使うようになった。
幸せなことに68kからPowerPC世代のさまざまな機種をいじった。
必要に迫られて触れるうちにソフトウエアの設計思想に魅了され、
自費でPowerBookという名のラップトップPCも購入した。
当時のApple社は業績不振、マックの廉価機種は処分価格になっており、
先進的なGUIに触れると、思いきって購入した記憶がある。
遊んでばかりで高価なおもちゃだったが、
GUIというものを理解したのは、その中で動いていた System 7 が初めてだ。
その後にジョブズ氏がApple社に復帰、iMacを発表してApple社が復活した。
そのニュースを聞いたとき、自分のマシンには創業者の手が入っていない、と拍子抜けしたのを覚えている。
(マイマシンは、ハードウエアとしては欠点が多々あった。)
その後、周囲の環境がWindowsに。しぶしぶ自分もWindowsに移行。
業務でOfficeを使う必要性から、やがて私物PCのOSもWindows XPへ。
その後、Windows系マシンを3台、CE系マシンを4台、購入しつつも、
Apple社の新製品発表は必ずチェック、いつもMacの世界へ戻る機会を探していた。
漠然と待ち望んでいた機会とは、いったい何だったんだろう?
Legacy deviceの撤廃、Officeの移植、Intel製PCの採用、Boot Camp…
いつかは、WindowsやMacなどというOSの境界がなくなることを夢見ていたのかもしれない。
OSメーカーでは、OSの境界は無くせない。
OSを事業の柱としない新しいコンピューティングモデルこそが、OSという境界をなくすのではないだろうか。
OSを自社開発しつつも新しい事業を開拓し続けるApple社のコンピューター、Macintosh。
OSの境界がない世界でこそ、メインマシンには「Macintosh」を、と期待していたのかもしれない。
その大きな可能性をドライブしてきた一人が、しかし偉大な一人が途半ばで歴史に刻まれた。
2011年10月06日
愛知牧場(その4)
魔除け
G12
牧場内で売られていた蹄鉄。
G12
牧場内で売られていた蹄鉄。
-----
蹄鉄は扉に打ち付けておくと、魔除けになる、と聞いたことがある。
さて、鉄の玄関扉にどうやって打ち付けるか?
このときは、方法が思い浮かばずに購入は見送り。
何か良いアイデアはないだろうか。
なお、打ち付ける方向も重要とのこと。
愛知牧場、東名高速道路の東郷PAからも、徒歩でアクセスできるそうだ。
高速移動の気晴らしにも良い休憩スポットである。
お土産には、乳製品やソーセージ・ハム等がある。
次はクーラーボックスを持参せねば。
-----
育児日誌:
子どもが小さいうちに動物園に連れて行くと、
免疫ができ、感染症への抵抗力がつくと聞いた。
動物の持つ病原菌やウイルスと接触しやすいからだろう。
今回、息子も新しい菌との出会いがあったに違いない。
2011年10月05日
愛知牧場(その3)
牧場の秋空
G12
DPPで現像。
空と建物、木々の階調を両立させた。
RAW+JPEGだと書込スピードは落ちるが、イメージどおりの写真に仕上がる。
ファイル管理が面倒だが、しばらくRAWで撮り続けてみよう。
G12
DPPで現像。
空と建物、木々の階調を両立させた。
RAW+JPEGだと書込スピードは落ちるが、イメージどおりの写真に仕上がる。
ファイル管理が面倒だが、しばらくRAWで撮り続けてみよう。
-----
愛知牧場は、最近入場料が変わった?との噂を聞いた。
おそらく、中の動物園の入場料のことだろう。
駐車料金や、牧場内を散策する分には、お金はかからなかった。
そのほか、100円玉々で済む程度の「協力金」を払えば、各種アトラクションを楽しめる。
乗馬から、餌やり、花畑の迷路など。
息子が大きくなったらまた違った楽しみ方がありそうだ。
写真好きなら、ただ中を散策するだけでも十分に楽しめる。
被写体は様々だ。
この日も、熱心に写真を撮っていた人がいた。
カメラは、FujiのFinePix X100(35mm相当の短焦点レンズ)。
つまり望遠レンズが無くても、動物を撮らなくとも、楽しめるということだ。
2011年10月04日
愛知牧場(その2)
パワーハンド
G12
これで飼い葉おけが何個も運ばれていた。
運転手は、長靴姿がカッコいい若い女性。
飼料運搬のほか堆肥作り等、ショベルカーは牧場の必須道具。
学生時代、植物園で堆肥作りしたのを思い出した。
G12
これで飼い葉おけが何個も運ばれていた。
運転手は、長靴姿がカッコいい若い女性。
飼料運搬のほか堆肥作り等、ショベルカーは牧場の必須道具。
学生時代、植物園で堆肥作りしたのを思い出した。
-----
育児日誌:
先週から家族全員が風邪気味であったが、
週末のお出かけで、親のほうが風邪をこじらせてしまった。
まだ親の調子までは分からないので、息子は朝から超元気。
そういえば、昨夜は四つんばいになることが多く、
つかまり立ちをしたがっていた。
お出かけ先で年上の子どもにたくさん会ったが、
その影響が出ているのかもしれない。
2011年10月03日
愛知牧場(その1)
-----
育児日誌:
息子は、今のところ動物に対する恐怖がないようだ。
大きな牛を見ても、特に怖がることなく、興味津々であった。
一方で、半年早く生まれた連れの子どもは、牛におびえていた。
2011年10月02日
JPEG圧縮率の比較(G12)

若人
S30
秋の草花が盛りなため、昨日から、早朝に写真を撮っている。
おかげで体調も気分も良い。
上の彼岸花も、昨日の一枚と同様、
RawデータをRawTherapeeのNatural-1で現像。
花弁の脈までよく写っている。
-----
通勤かばんに放り込んでいるS30が、RAW現像によって
まだまだ使えることを発見してしまったため、
せっかく購入したG12の出番がない。屋内専用になってしまっている。
今日は、JPEGの画像圧縮率と画質についてメモ。
上の写真を二枚撮影し、等倍で細部を比較した。
その結果が下記の写真なのだが、
圧縮率が高いほうが、やや布の網目がつぶれている。
だが、ディスプレイで縮小して干渉する分には、
違いはファイルサイズほどは感じられない。
最近は、RAW/JPEGの切り替えをショートカットに入れてある。
RAWも撮り、JPEGの仕上がりが問題なければRAWは廃棄、で運用する。
2011年10月01日
言い訳を無くす

天啓
S30
S30
-----
夕食を食べながら、なぜか突然、頭に次の言葉が浮かんだ。
トップダウンのテーマは、短期決戦。
経営サイドから、専門性の高いテーマが指示されたことがある。
そんなテーマは事業化まで10年単位の仕事だ、と現場では感じられたのだが、
期中に1年以内に成果を出すことを求められた。
景気や外的環境変化、組織変革等により、経営方針が変わるため、
経営サイドの評価はスピード重視だ。
(1年以上好業績が継続するなどありえないからだ。)
評価期間が短いと成果も出しにくく、結果として短期のテーマとなることが多い。
これと反対なのが、ボトムアップのテーマや外部とのコラボレーション。
事業部門のトップに理解してもらうことは必須だが、現場の意気は勝る。
よって、中長期にわたり継続しやすいのではないだろうか。
この好対照な理由は、担当者が「止める」言い訳を持つか持たないかだと思う。
トップダウンで始めたのだから、止めろと言われれば続ける筋合いはない、
という正論に逆らってまで続けることは難しいだろう。
さらにこの両者の特徴を深めると、注意すべき点が見えてくる。
トップダウンテーマは、納期に関係なく、できる限り早く成果を見える形にする。
たとえ当初のスケジュールがあったとしても、上の一声で短縮されうる。
「止める」言い訳を考える暇があったら、一定の結果を残したい。
ボトムアップテーマは、潮時が見えにくい。
ずるずると引きずられ時を無駄にするリスクが隠れている。
マネジメント不足を言い訳にしたくない。
自ら撤退基準となる線を事前に引いておく必要がある。
-----
〔〕 periodic 定期的な
定期的に今の仕事を見直す時間が欲しい。
オーバーフロー状態なのは相変らずだ。
-----
育児日誌:
鼻かぜを引いているようだが、元気に遊んでいる。
寝るときの呼吸は少ししんどそうだが。